2022.12.06
ウェルビーイングな社会をつくる① ~「好きなこと」をやる勇気を持とう~【前編】
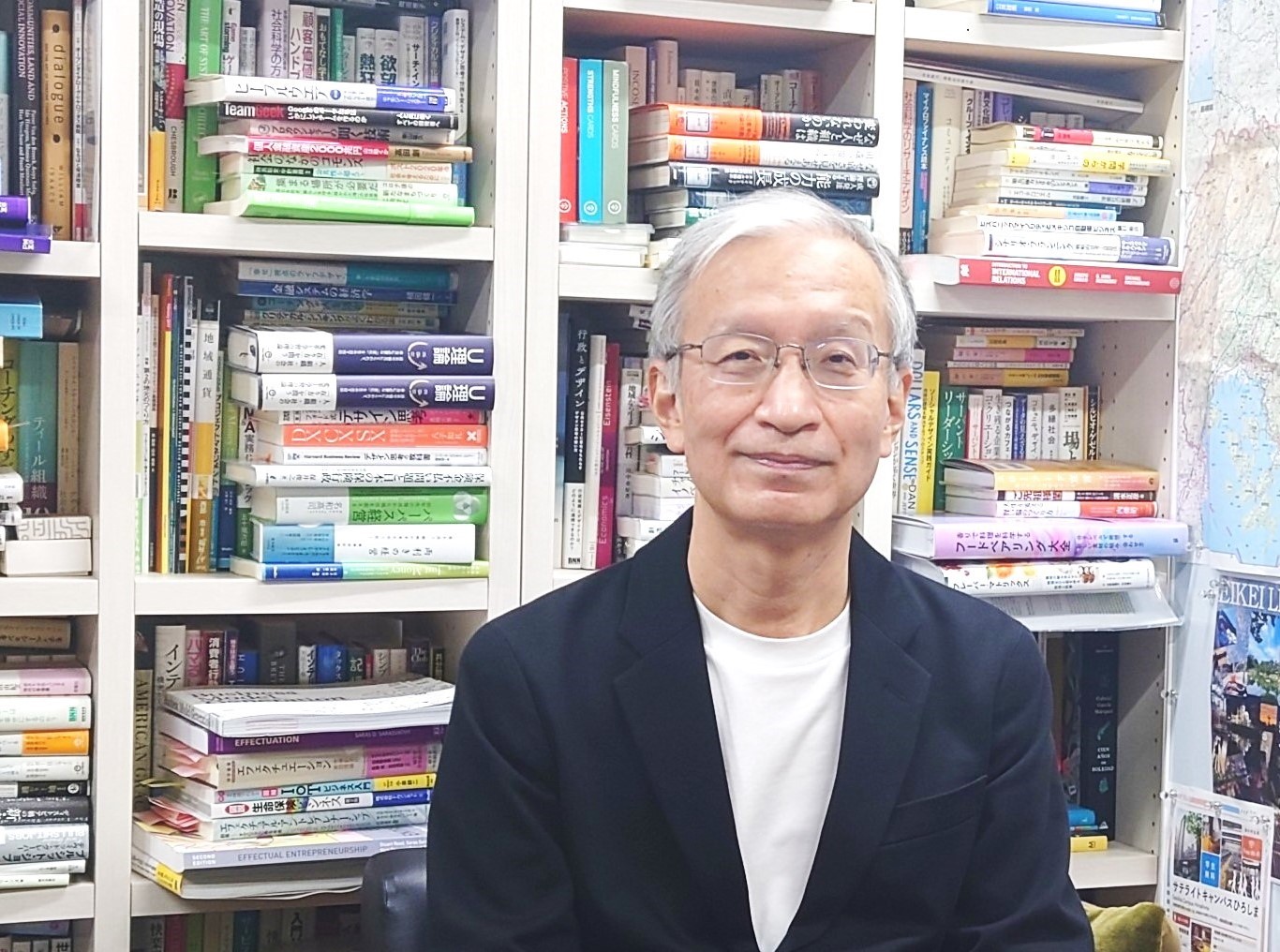
【保井 俊之先生プロフィール】
広島県公立大学法人 叡啓大学 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長 教授 兼 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特別招聘教授1985 年東京大学卒、財務省及び金融庁等、パリ、インド並びにワシントンDC の国際機関や在外公館等に勤務したのち、地域経済活性化支援機構常務取締役、国際開発金融機関IDBの日本ほか5か国代表理事等を歴任。慶應義塾大学大学院で2008年から教壇に立つ。2011年国際基督教大学から学術博士号。米国PMI 認定Project Management Professional。日本創造学会評議員、地域活性学会理事兼学会誌編集委員会委員長、PMI日本支部理事、ウェルビーイング学会監事、一般社団法人エミーバンク協会理事兼最幸顧問。
これからの社会がよりウェルビーイングであるために、私たち一人ひとりが、そして企業はどうあるべきなのでしょうか?そのヒントを2回にわたり保井俊之先生にインタビューしました。
保井先生は、叡啓大学などで学生や社会人に向けてイノベーションを起こすための学びやつながりの場を提供しているほか、多数の企業や団体とウェルビーイングを中心とした事業開発や取り組みを行うなど幅広く活躍されています。
第一回は、保井先生が幸せの研究者になるまでのユニークなご経歴や、人生観が大きく変わった出来事、大人になってから何かを始めたいと思っている人たちへ向けたメッセージなどを伺いました。
“うわさ話”を信じて決めた進路
―保井先生はこれまでに、財務省や金融庁、いわゆる官民ファンドの常務など、お金に関する仕事をされていましたよね。そういったご経歴がありながら、現在は「幸せ」についての研究者であり教育者をされていますが、そこにシフトしたきっかけは何かあったのでしょうか?
ずっと大学の研究者になりたいとは思っていたんです。だからそういう道を歩んできてはいました。音楽も好きで、小学生のころから音楽をやっていて、ブラスバンド部でトロンボーン、大学時代は尺八を吹いていました。尺八というのは、独奏で自分のパートも完璧にこなすし、合奏でもきれいな音楽ができる楽器なんです。自分自身のパートを分析すること、それから全体を俯瞰すること、というこのふたつが美しいものをつくるのにとても役立つということを実感したので、こういったことを勉強したり研究したいと思い、大学では国際関係論を勉強することにしました。国際関係論とは、国と国の関係や個人・非営利団体と国際社会の関係などを分析する学問なので、全体俯瞰が必要なんです。関係性がつながっていくことを考えながらいろいろなものをつくり、それで何かが変わっていく。そこに魅せられました。そのころから研究者になりたいと思っていたのですが、家計の事情があり、いったんはそこで研究者の道を諦めて卒業後は就職することにしました。日本育英会(現在の学生支援機構)の奨学金を借りていたのですが、当時は「国家公務員になれば返さなくていい」という根も葉もないうわさがありまして、それを無邪気に信じ、財務省(当時の大蔵省)に面接に行きました。その時に、面接官だった人事担当の方に「君は日本が好きか?」と聞かれたので、「はい」と答えたら握手をされて採用が決まりました。あそこにはおもしろい人たちがたくさんいるんですよ(笑)
財務省には10年ぐらい勤めて、そのあとは研究者の道に進むために大学院に進学しようと思っていたのですが、そこで奨学金のうわさが本当ではなかったことを知りました。それを返すために、一生懸命がんばっているうちに財務省の仕事が面白くなり始めたんです。財務省というのは、高齢化もそうですし過疎や社会福祉など、いろいろなところからこじれまくって大変なことになっているお金がらみの問題がどんどん放り込まれてきて、それを「さあ解いてくれ」といわれるところです。それがおもしろくなり、結局35年間勤めました。
入省して15年ぐらい経ったころ、「何かおかしいな」と思い始めました。財務省のすごく優秀な人たちが朝方まで仕事をし、また朝9時になったら出勤する、という毎日を過ごしていましたが、そんな環境でつくった解決策というものは、何か違うのではないかと。こういう生活をし、なおかつ肩書を背負っているので、例えば「私」が個人として小宮沢さんという人に話をしているのに、「財務省といたしましては」というように、「財務省」が小宮沢さんの会社に話をしている感覚になってしまう。これは、立場や肩書を外さないと問題解決にも何もならないと思いました。
そこで、小さなステップですが少年サッカーのコーチを始めました。サッカーのコーチとは、ひとつの目的のために多様な人たちがつながってひとつの価値をつくる役割です。これはおもしろいことだと気付き、こういった「つながりが価値を生み出す」ことを研究していきたいと思いました。
人生の転機―911に遭遇して
2001年の7月にワシントンD.C.のシンクタンクへ赴任することになり、日本から家族と共に移ったのですが、研究者の道に進む直接のきっかけになったのがちょうどこの頃でした。その年の9月11日、出張でニューヨークのワールドトレードセンターの中のマリオットホテルに泊まっていました。部屋の中にいたら飛行機が突っ込んできたんです。急にブザーが鳴り、とにかく下に逃げろと誘導され、そこから南に3キロメートルほどのバッテリーパークというところまで走って逃げました。逃げるさなかに二機目が頭の上を飛んでいき、ビルにのめり込んでいきました。2つのタワーががっくりと膝をつくように崩壊していくのが見え、私はアスベストの入ったほこりをかぶり全身真っ白になりました。マンハッタンは州兵と警察により完全に閉鎖され、そこから3日間出られませんでしたが、親切な人がその方のアパートに泊めてくださいました。3日目にようやくレンタカーを借りることができたので、同僚と2人で5時間かけてワシントンDCの自宅へ帰りました。ずっと携帯もつながらない状態だったので、帰宅したら妻ははすごく驚いて最初に私の足を見ました。お化けだと思ったようです(笑)。
これまでは、一生懸命に役所の仕事をして出世していこうと思っていたのに、それがここで一気に変わってしまいました。9-11テロで3000人ぐらいの方が亡くなりましたが、なんで自分は生き残ってしまったんだろうという罪悪感に駆られ、心的外傷後ストレス障害(PTSD)にもなりました。つらい思いで2年間ぐらい過ごしているうちにPTSDも解けてきて、今度はなぜ9-11のようなテロが起きたのだろうかと考え始めました。テロリストが憎いと言うのは簡単なことですが、それを言っても原因と結果は変わりません。これは米国の特別国家委員会がとりまとめた『9/11レポート: 2001年米国同時多発テロ調査委員会報告書』にも書かれていることですが、結局のところアメリカは、自分で自分の足を打っていたということなんです。9-11の原因として、まずソ連がアフガニスタンに1979年に侵攻したときに、米国の情報機関CIAの人たちがムジャーヒディーンといわれるアフガンのゲリラの人たちを支援しました。ムジャへディーンの戦士たちはCIAの支援で資金をつくり、武器を得て、ソ連軍を撤退に追い込みました。しかし、サウジアラビアなどから来ていたそのムジャーヒディーンの人たちは、母国に帰ってもほとんど歓迎されなかったのです。彼らが落胆していた時はちょうど湾岸戦争の時代でした。当時アメリカ兵たちが、ジェッタやリヤドなどムスリムの聖地の都市でTシャツを着て闊歩していたのですが、それが宗教的な侮辱のように捉えられ、彼らは次第にアメリカを憎むようになっていったんです。そして、サウジアラビアの王族の一部の人たちがお金を出し、彼らをパイロット学校に入れ、テロリストを養成して飛行機で突っ込んでいく。そういった関係性のつながりで、因果がぐるっと回っているということは国際関係論を学んでいたので理解できました。そして、システム思考という因果やつながりに着目した学問があることを知り、それからシステム思考を本格的に勉強するようになりました。
やはり憎しみや貧困、偏見といったものが因果として回っていき、それがテロを引き起こしたというのであればひっくり返したいです。その人らしい寛容さや喜び、幸せというもので悪い因果をひっくり返せたら、きっと世の中のみんなが幸せになっていく。今度はそんな学問がないのかと思っていた時に、それがデザイン思考だと知り勉強しました。
幸せの研究者の道へ
そうしているうちに、2008年に慶応義塾大学大学院にシステムデザイン・マネジメント研究科ができ、そこで教えてみないかと言われました。当時は子供たちも小さかったですし、財務省からはお給料をもらっているので、夜と週末に無給教員として教え始めました。そこで幸福学の日本の第一人者である前野隆司先生と出会い、心の幸せすなわちウェルビーイングの共同研究をしていく中で、つながることが幸せになるとか、それを加速するためにはどうしたらいいのだろうということが私の専門になりました。社会が幸せになるために、社会システムや社会のイノベーション、地域やお金はどうデザインしていけばいいのだろうか、ということにのめりこんでいきました。当時は官民ファンドのひとつ「地域活性化支援機構(REVIC)」の役員として、地域の事業再生や地域活性化ファンドづくりのために全国を行脚していました。地域では、悲しい言葉ですが、ご縁が切れてお年寄りが孤独死するといった「無縁社会」化が進んでいるところもあり、そういった地域がどうしたら元気になるか。これもやはり、つながることがウェルビーイングになっていく、というひとつのあり方も私の研究テーマとなっていきました。
なぜ霞が関の国家公務員がウェルビーイングの研究者になったのか。それは最初からなりたかったわけですから、私としては「ようやくここに戻ってきた」ということなのです。
取材・文/小宮沢奈代


